Algomatic CHRO 高橋氏に聞く、 AI時代に求められる、候補者一人ひとりと向き合う採用戦略
2025.03.06

AIが急速に発展する昨今、AIを日々の業務に取り入れることは必須になってきています。今回は、AIを採用領域に取り入れサービスの開発・提供している株式会社Algomatic CHRO 高橋 寛行氏 (以下、高橋) に、AI時代の採用への活用方法やポイントについて、採用イネーブルメントSaaS 「RekMA」を運営するHaul 代表取締役 平田が対談を行いました。
プロフィール:高橋 寛行(株式会社Algomatic CHRO)
2005年株式会社インテリジェンス(現 パーソルキャリア株式会社)にて人材紹介に従事し、2010年より株式会社ミクシィ(現 株式会社MIXI)にて人事キャリアをスタート。2012年株式会社コロプラへ入社、採用・制度企画・労務等の人事全般を経験。2016年からは株式会社メルカリにて中途採用・新卒採用の立ち上げ、People eXperience(制度企画・労務)に従事。2019年より株式会社ヤプリで人事部長を務めたのち、2023年より株式会社hacomono CHROとして従事するなど、人事として3度のIPOを経験。2024年1月よりAlgomatic CHROに就任。2024年8月よりAlgomatic Worksにて事業開発を兼任。
人材紹介、事業会社人事、そして事業開発のキャリアへ

ーー まずは高橋さんのこれまでのキャリアや経歴について教えてください。
高橋:2005年、旧インテリジェンス(現パーソルキャリア)に入社し、人材紹介業に従事し、企業向けのリクルーティングアドバイザー(RA)および求職者向けのキャリアアドバイザー(CA)を経験し、約4年間勤務しました。
その後、事業会社の人事に転身し、ミクシィ(現MIXI)に入社しました。当時250名規模だった同社において、中途採用を中心に人事業務を担当し、500名規模へと成長する過程を経験しました。
次に、社員数100名弱だったコロプラへ転職し、マザーズ上場および東証一部への市場変更を経て、1,000名以上への拡大期を経験しました。ここでは採用業務に加え人事労務や制度設計など、人事全般を担当しました。
その後、メルカリに入社し約4年半在籍しました。当時100名規模だった組織が、IPOを経てグローバルで約5,000名規模へと成長する中で、中途・新卒採用のほか、インセンティブ制度や組織制度の設計にも携わりました。
BtoB SaaS領域の勃興期に魅力を感じ、ヤプリに転職し、人事部長として4年間在籍し人事全般を統括しながら、ここでもIPOを経験しました。
その後、hacomonoでCHRO(最高人事責任者)を1年間務め、2024年1月よりAlgomaticに参画し、現在に至ります。
― 現在のAlgomatic社では、横断的なCHRO(最高人事責任者)と「Algomatic Works」の事業開発を兼務されていると伺っています。具体的な役割を教えてください。
高橋: 前提として、Algomaticは生成AIを主軸として複数の事業を展開しています。その一つに、「生成AIを活用したHR領域の事業」を開発・運営している「Algomatic Works」という子会社があり、私自身はCHROという役割はほぼ肩書きのみで現断面においてはその事業開発に99%の時間を注いでいます。
これまでのHR領域での経験を活かし、「どのような課題があるのか」「AIがどのように関与すると解決できるのか」について、開発メンバーたちと議論を重ねています。
さらに、開発したサービスの提案・販売におけるセールス活動に加え、導入企業の支援を担うカスタマーサクセス業務にも従事しています。
平田:これまでの人事の経験を事業開発に活かされていますね。特に、AIとHRの掛け合わせは、今後の可能性が広がる分野だと思います。
高橋:AIの活用により人事業務が大きく変革していくことはもちろん、HR領域に従事する私も含めた人事のみなさんのキャリアの選択肢が広がることになるなと感じています。事業開発やセールス等に人事の経験を応用できる場面が増え、これまでの大半のケースである「採用や労務のスペシャリストになるのか?」「人事責任者やCHROなどのマネジメントを目指すのか?」から、それ以外の”ドメインエキスパート”という第三の選択肢が出てきたということでもあると実感しています。
小さな成功体験から全社採用の文化を作る

― さまざまな企業で採用や組織づくりを牽引されてきた中で、「経営視点を持った採用」という点について、高橋さんはどのように考え、推進されてきましたか。
高橋:これまで在籍してきたスタートアップやベンチャー企業では、「優秀な人材をいかに迅速かつ多く採用できるか」が、事業成長の鍵となっていました。採用は、事業の成長を加速させる推進力であると同時に、最大のボトルネックにもなり得ます。
また、採用活動そのものが企業のカルチャーを形成する重要な要素であると考えています。
例えば、「採用は人事の仕事」という雰囲気が醸成されると、それが企業文化としてセクショナリズム(縦割り意識)の体現になり、割れ窓理論的にこれを防げないとその先は意図しない企業文化になってしまう未来が待っている、その大きなきっかけになりうると考えています。
一方、私が知る限り組織が強いと言われているスタートアップやベンチャーでは、例外もれず採用に限らず「全員採用」「全員営業」「全員コーポレート」といったカルチャーとモメンタムを早い段階から形成し”当たり前化”していっているように思います。この”当たり前”に全員が採用にコミットしているから採用もうまくいくし、その一体感や連動性が組織としての魅力にもなり、また優秀な人が集まる・・・というスパイラルを意図的に形成しています。そのためのまずは最初の一歩、きっかけづくりの一つとして「採用を全社で取り組むべきもの」というカルチャーの浸透からはじめ、これまでの企業において採用の仕組みを構築してきました。
平田:「全員で取り組むもの」として採用を位置づけることが、企業文化につながることは、とても納得感があります。
高橋:例えば、リファラル採用を活用することで、組織づくりの楽しさを体感してもらうのも重要なポイントです。スタートアップやベンチャー企業に入ったからこそ、組織上の自分の役割のみをこなすだけでなく、会社目線・経営目線で「組織をつくることの面白さ」も、そういった企業で働く醍醐味の一つだと考えています。
平田:メンバーが採用に関わる際、採用を自分事化できるように、仕組としてどのように工夫をされてきましたか。
高橋:重要なのは「小さな成功体験を積むこと」だと考えています。
例えば、「この人と一緒に働きたい」と思った場合、まずはその気持ちをチームに共有してもらうことから始めます。その結果、実際にその人が入社し、同じチームで働くことになれば、採用の意義を実感できますよね。
また、入社後のオンボーディングでも、先輩社員がメンターとして新入社員を支援する経験を通じて、「次に新しいメンバーが入社したとき、自分も同じようにサポートしよう」と思うようになります。
こうした小さな成功体験を積み重ねることで、採用活動が組織全体の文化として根付いていくと考えています。
組織を強くするには、全員が納得する”背中を預けられる人材”の採用
― 小さな成功体験を積み重ねることで、採用活動が文化として根付くというお話、とても共感します。では、Algomaticさんでは、どのような採用文化を作っているのか教えてください。
高橋:まず、「全員採用」という文化は、もともと会社のベースに根付いています。
そのため、採用に関わるのは人事だけではなく、事業責任者やその他のメンバーも積極的に取り組んでいます。
私たちは創業間もないスタートアップだからこそ、「持たざる者の戦い方」を意識し、全員で採用に取り組む中で「諦めが悪い採用」を大切にしています。
例えば、私たちの採用スローガンの一つに「この人と働きたいと思ったら、10年かけても口説く」というものがあります。
3年後や5年後ではなく、10年かけてでも関係を築き続けるという考え方です。
一般的に「今回のタイミングでは縁がなかった」と諦めてしまうことが多いですが、「数ヶ月後や数年後には状況が変わるかもしれない」と考えています。だからこそ、一度ご縁があった方とは、長く関係を築いていくことを大切にしています。
平田:そうした採用に対する向き合い方の中で、「優秀な人材」をどのように定義し、見極めているのでしょうか。
高橋:Algomaticでは「能力密度」という言葉をよく使います。これは、「優秀な人にとって最大の福利厚生は、優秀な人と働くこと」という考えに基づいています。採用の段階で、全員が納得できるレベルで「この人に背中を預けられるか」を大事にし、「能力が高く、水準が高い人」を採用することで、その密度が濃くなり、組織としての生産性が向上します。
AIによって人事担当者が本質的な業務に集中できる

― 採用においてもAIの活用が進んでいますが、AIが採用に与える影響をどのように捉えていますか。
高橋:AIの活用によって、「採用プロセスにおける人事に求められる能力のポイント」が大きく変化すると考えています。
例えば、候補者が自分のレジュメをどこかしらの転職マーケットにアップロードすると、AIが即座に適した企業をピックアップしてくれるようになるかもしれません。
これまでなら、自分で検索をして探したり、人材エージェントと相談しながら応募企業を選んでいましたが、AIの活用により、瞬時に企業カルチャーのマッチングも含めた内定確度の極めて高い最適な企業が提案されるようになるなどの可能性は十分にあると思います。つまりそれは同時に、企業側においては、応募者の母集団形成や書類選考という人事として決して少なくない時間を投下しているものがほとんど不要になる未来になるということです。そうなった時にこれからの人事の方々が本当にやるべき、本当に求められる能力が変化する、もしくは研ぎ澄まされていくのではないかなと思っています。
平田:AIによって、採用プロセスが効率化される一方で、「人の判断がより重要になる場面」も増えると考えています。
高橋:おっしゃる通りです。AIによるルーティン業務の自動化により、人事担当者は「人間ならではの価値を発揮できる業務」に注力できるようになります。
具体的には、候補者との深いコミュニケーションや、企業文化の発信、入社後のオンボーディングの設計などが挙げられます。つまり、AIは人の仕事を代替するのではなく、「人が本質的な業務に、より集中できる環境を作るもの」だと捉えています。
― AIの活用によって採用プロセスが効率化されることで、人事担当者が本質的な業務に集中できる環境が整うわけですね。では、AI時代における『採用チームの役割』については、どのようにお考えですか。
高橋:AIの発展により個人の生産性が飛躍的に向上することを、少なくとも弊社事業では目指しています。
一方で、採用チームの基本的なあり方は大きく変化しないと考えています。その前提で、採用チームの組織設計には、主に2つのアプローチがあります。
1つ目は「プロセスごとに担当を分ける方法」です。
例えば、母集団形成担当、レジュメスクリーニング担当、カジュアル面談担当、選考担当…といったように、細かく分業するやり方です。これは採用版の「The Model」と言えるかと思います。
2つ目は、「リクルーター制」です。ポジションごとに専任のリクルーターを配置し、母集団形成から内定承諾まで一貫して担当するやり方です。
平田:「The Model型」と「リクルーター制」のどちらのスタイルがよりAIに適していると考えていますか。
高橋:それぞれ特徴的な利点があります。
「The Model型」を採用しているチームでは、もともと分業されているので特定のフェーズを切り出してAIに移行するというのは比較的スムーズだという利点があります。レジュメのマッチング判断やスカウトの自動化が進むことで、その工程や領域と人事との分担・協業はシームレスにできる可能性が高いです。
一方、「リクルーター制」を採用しているチームでは、AIは補助的な役割を担うものの、リクルーター本来の役割に大きな変化は生じないと考えられます。リクルーターとしての役割や守備範囲はそのままでAIと協業しながら、AIをマネジメントする立場になるようなイメージです。AIによるルーティン業務の効率化により、リクルーターには候補者との深い関係構築など、より高度なリクルーティングの実行が要求されるようになると考えています。
平田:採用プロセス全体の候補者への向き合いにおいて、「候補者体験」を向上させるために意識していることはありますか。
高橋:候補者体験を向上させるには、「企業広報のマインド」を持つことが大切です。
候補者は「単に採用の可否」だけではなく、企業の本質や社員の特徴など、組織全体への理解を深めたいと考えています。このように、候補者を未来の顧客やパートナーとして捉える視点を持つことで、採用プロセス全体のあり方が変化します。
また、選考を通過しなかった候補者であっても、「心地の良い選考体験だった」という印象が残れば、将来的に採用するということに限らず自社といつか何らかの形で良好な関係を築ける可能性もあります。反対に、不適切な選考定件の提供は永続的な企業への否定的な印象を生み、企業ブランドはもちろんサービスやプロダクトに対するレピュテーションにも大きな影響をあたえかねません。そのため、採用活動を企業ブランド構築の重要な機会と位置づけ、すべての接点において丁寧な対応を心がけています。
顕在層から潜在層へ。タレントプール構築 x AI が鍵

―現在の採用市場は、ここ数年はどのように変化すると捉えていますか。
高橋:言わずもがな転職市場の変化として、「転職顕在層」だけをターゲットとした採用活動では、十分な成果を得ることが困難になってきています。
従来は、転職エージェントや転職媒体の活用により、一定の採用効果を実現できていました。
現在は「既に転職を検討している人材」の獲得競争が激化しており、従来型のアプローチだけでは必要な母集団を形成することが難しくなっています。
このような状況下で、「転職を積極的に検討していない潜在層へのアプローチ」もしくは「転職を今まさに考えようとしている人の意向を早期にキャッチすること」がより重要性を増しています。
具体的には、現時点では転職意向がない・これから検討をはじめるという方で、スキルや経験が自社の要件に合致する人材との関係構築を、早期から戦略的に進めていく必要があります。
平田:転職潜在層へのアプローチ方法として、どのような施策が有効だとお考えですか。
高橋:この課題に対する有効な解決策の一つとしては、「タレントプールの構築とその鮮度を保つこと」だと考えています。
これは、潜在的な入社候補者との関係を、転職意向の有無に関わらず継続的に維持・発展させる体系的なアプローチです。
具体的には、「以前、カジュアル面談をしたが、そのときは転職を考えていなかった人」に対して、定期的な情報提供や企業の最新動向の共有を行います。
特に、SNSやオウンドメディアを活用し、企業のカルチャーや働く環境について積極的に発信することで、自然な形で候補者の関心を引くことができます。
このような継続的な取り組みにより、転職を積極的に検討していなかった人材からも、企業への関心や対話の意向を引き出すことができます。
平田:タレントプールや情報発信を通じて、転職潜在層と継続的に関係を築くことは重要ですね。こうしたアプローチを強化する中で、AIの活用はどのような影響を与えると考えていますか。
高橋:AIの活用により、適切な候補者との接点構築のタイミングをより戦略的に判断できるようになると考えられます。
例えば、過去の候補者のデータをAIで分析し、特定のスキルセットを持つ人材の転職活動開始時期を、過去のトレンドに基づいて予測することが可能になるでしょう。
さらに、企業側のデータの活用により、特定の経歴を持つ人材の採用に成功した企業の事例や傾向を分析することが可能になります。これらのデータに基づいた戦略的アプローチにより、従来の網羅的なスカウト配信から脱却し、最適なタイミングで最適な候補者にアプローチできる体制を構築することが可能となると考えられます。
柔軟な戦略と長期視点が未来をつくる
― 最後に、これからの採用活動において、企業が意識すべきポイントを教えてください。
高橋:フルタイム雇用は、これまでのような標準的な選択肢ではなくなりつつあります。プロジェクトベースでの人材活用やギグワーク (雇用関係を結ばない単発・短時間の働き方) など、より柔軟な働き方を導入する企業が増えています。これまでの『採用=正社員を雇うこと』という固定観念を捨て、正社員に限らず、業務委託、フリーランス、副業といった多様な働き方を前提にした柔軟な採用戦略を考える必要があります。
さらに、候補者との関係構築においても、長期的な視点の重要性が高まっています。
「今すぐ採用する」という視点だけでなく、「数年後にこの人と一緒に働くために、今どのような関係を築くと良いか」と考えることが、これからの採用の鍵になるでしょう。
そして最も重要なのは、「採用は経営の本質的な機能」として位置付けることです。
優秀な人材の獲得は、事業成長の重要な推進力となります。このため、採用活動を人事部門の独立した機能としてではなく、経営戦略の核心的要素として捉え、組織全体で取り組むべき課題として認識する必要があると思っています。
平田:採用の未来について、非常に多くの学びと、示唆に富んだお話を伺うことができました。本日はありがとうございました。

各社のサイトURL
株式会社Algomatic:https://algomatic.jp/
株式会社Haul:https://haulinc.jp/
基礎から実践までこれ一冊で学べる
アトラクト採用を即実施できるガイドブック配布中
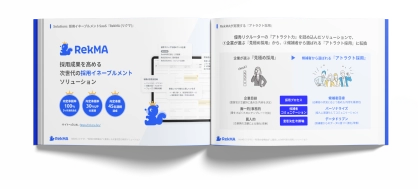
お問い合わせ
ありがとうございました。
こちらのリンクから
資料をダウンロードしてください。
